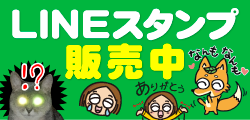- ホーム
- 伝わる!広告デザイン研究室
- デザイン
- デザインに必要な要素(肉付け)とは(その2)
デザインに必要な要素(肉付け)とは(その2)
2022/01/16
大ラフと、手書きの大まかなラフができたら
準備は完了!と言いたいですが。ここからが結構大変なんです。
なんたって、大ラフやラフはほぼほぼ墨一色か鉛筆で書いてる状態ですのも、そんな状態ではデザインとはいえませんよね。
ここから重要なのは、その商品にとって色付けが重要か?
商品がナチュラル系の飲み物やフードだったりしましょう。
その商品の広告を紫や真っ赤なイメージのデザインで仕上げたとしましょう。購買意欲がわきますか?
感覚的に、その商品を手にすることはあまりないと思います。
顧客(ユーザー)が好むべき、商品カラーイメージが決まった時、全て同じような色で構成してはもったいないデザインになってしまいますので、イメージした色を決めた後にする作業といえば、レイアウトで文字の棲み分けの作業が必要です。
リウムスマイルの穂口さんも、タイトルやあしらえの統一感を持たせてブログをすっきりとしたレイアウトにとお勧めしていることもありますように、紙面やバナーといったデザインものにもある程度のルールが必要になってきます。
以前は簡単だったのでが、昔の印刷物は使うツールが少なく、手書きが主流だった頃は、ノートなどにメモを撮る感覚といったらわかりやすいでしょうか?取りたいメモでココが大事と思った文章やコメント並びに直接思った感想など、重要な箇所は強調(太字)したり、下線やマーカーなどで印をつけて見やすくしますよね。それと、同じようにデザインでもタイトルや日時などお客様に伝えわかりやすく強調する場所が必ずあります。
その後、印刷も活版印刷や写植版下時代を経て、現在ではコンピュータを使用したデザインに移行した時代になり、デザイン物の汎用性も増えました。現在ではデザイン会社に頼むこともなく、各でイベントや商品販売のための広告物を自作されている方も多く見受けられます。自作される又はデザイン会社に依頼される時に何を大事にするのか?
タイトル、サブタイトル、本文のこれらが同一の大きさと同じような色で配置された場合、どの文章に目がいきますか?
タイトルが本文に埋没されて、視認されることはまずないといっても良いでしょうね。
紙面が大きくなればなるほど、目線の誘導も難しくなってきます。人の目の認識にかかる時間は少なく、0.6秒から1〜2秒とされています。そのような時間内により広告物のデザイン力をあけげるのかは、レイアウトによって決まってきます。
では、タイトルを(大)としてサブタイトルを(中)、そして本文を(小)とすれば良いのかといえばそうですと言えるのですが、これはあくまでも流れをよくするために大きさのバランスを言ったまでで、実際にはタイトルの内容に対して、サブタイトルの配置を考え、その後に本文がくるパターンはさらっとしすぎる感があります。
よくある市場の広告で、「○○鮮魚感謝際」などあった場合はサブタイトルより次にくる文章は何か、「お客様の望むもの」と考えるのがセオリーなのでここは○月○日朝○時オープンなど時間をお伝えして、その後にサブタイトルで「○○港直送鮮魚、マグロ大放出」などのサブタイトルと合わせる感じです。
まあ、チラシの本文といえば各、目玉商品の名前と値段ですが、目玉商品が(大写真と・商品コピー)お勧め商品が(中の写真)、日常品(小・文章だけ)などと、どの商品に目がいくか、考えてレイアウトすれば良いと思います。
レイアウトに基本は存在はしておりますが、感覚的にいえば左上から始まり、Z字(左から右へ、右から、左下へ目線の移動)のようにレイアウトにお客の目線を誘導していき、最終的に全てを読ませるのかセオリーになっていると思います。
ですが、世の中の商品全てが同じセオリーで広告を作っていたら面白みにかけるというか、お客(顧客)も見飽きてしまうでしょうね。
時に、変則的なデザインも必要で、中心に大きなタイトルがあっても良いでしょう。その場合も、次の目線をどこに向けるのか?タイトルに目がいくと同時に、内容は何?といった真理を上手くキャッチして次の目線をどこに配置するかという感じで、ラフデザインをする上で何回か繰り返すと良いと良いでしょう。
面倒くさくても、この作業をするしないで広告の出来栄えは変わってきますので試してみてください。
次は、フォントについてお話は続きます。
-
 似顔絵もここまで使われると本望です!
暑い日が続いている札幌。とはいえ本州の方に比べたらまだまだ涼しいので弱音は控えたい…スタジオシンカーやまたに家
似顔絵もここまで使われると本望です!
暑い日が続いている札幌。とはいえ本州の方に比べたらまだまだ涼しいので弱音は控えたい…スタジオシンカーやまたに家
-
 ホームページは●●を発揮したらいい!
昨日7月11日(月)はオンライン(zoom)にて、分身ホームページ『穂口になんでも聞けるで会』好物食べ
ホームページは●●を発揮したらいい!
昨日7月11日(月)はオンライン(zoom)にて、分身ホームページ『穂口になんでも聞けるで会』好物食べ
-
 好きなお客様に選ばれたい!〜ホームページって役立つの?
個人で活動、スモールビジネスを応援!! 広告デザインのスタジオシンカーやまた
好きなお客様に選ばれたい!〜ホームページって役立つの?
個人で活動、スモールビジネスを応援!! 広告デザインのスタジオシンカーやまた
-
 デザインは自由に!トキメキを大事に〜趣味もデザインに活かせる♪
先日、小樽のガラス作家 SHiMA SHiMAさんに誘われて、なわ あいさんの「アルコールインクアート」のワー
デザインは自由に!トキメキを大事に〜趣味もデザインに活かせる♪
先日、小樽のガラス作家 SHiMA SHiMAさんに誘われて、なわ あいさんの「アルコールインクアート」のワー
-
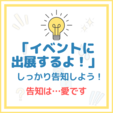 「イベントに出展するよ!」しっかり告知しよう♪告知は…愛です
イベント出展は知ってももらえるチャンス!出展のその前にしたいこと。 自分のお店を離れて、イベントや●●展に出展
「イベントに出展するよ!」しっかり告知しよう♪告知は…愛です
イベント出展は知ってももらえるチャンス!出展のその前にしたいこと。 自分のお店を離れて、イベントや●●展に出展


広告デザインのスタジオシンカー[やまたに家]
デザインはあなたが羽ばたく翼になる!
まずはお気軽にお問合せくださいね。
電話番号:011-785-2873
所在地 :北海道札幌市東区北23条東16丁目1-19 2F
営業時間:9:30〜18:00
定休日 :不定休